0.8.5 シューア補行列と行列式の公式
\(A = [a_{ij}] \in M_n(F)\) とし、ある添字集合
\( \alpha \subset \{1, \ldots, n\} \) に対して、部分行列 \( A[\alpha] \) が正則(可逆)であるとします。
このとき、\(A\) の 2-分割に基づく行列式の重要な公式は以下の通りです。
\det A
= \det A[\alpha] \cdot \det(A[\alpha^c] - A[{\alpha^c,\alpha}] A[\alpha]^{-1} A[{\alpha,\alpha^c}])
これは 2×2 行列における行列式の公式の一般化です。式中の
A / A[\alpha] = A[\alpha^c] - A[\alpha^c,\alpha] A[\alpha]^{-1} A[\alpha,\alpha^c]
は \(A\) における \( A[\alpha] \) に対するシューア補行列(Schur complement)と呼ばれます。
この式は、(0.7.3.1) における逆行列の分割形式にも登場します。
シューア補行列は、ブロックガウス消去を用いて導かれ、以下の恒等式を用いて証明できます:
\begin{bmatrix}
I & 0 \\
- A_{21} A_{11}^{-1} & I
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
A_{11} & A_{12} \\
A_{21} & A_{22}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
I & - A_{11}^{-1} A_{12} \\
0 & I
\end{bmatrix} =
\begin{bmatrix}
A_{11} & 0 \\
0 & A / A_{11}
\end{bmatrix}
ここで \( S = A / A_{11} \) をシューア補行列とします。
Schur補行列の性質:余因子・階数・行列式
(a) Schur 補行列 \(S\) は、行列 \(A\) の最初の \(k\) 行(列)について線形結合を取り、残りの \(n-k\) 行(列)に加えることで、左下(あるいは右上)のブロックを 0 にする際に、右下に一意的に現れるブロックである。この操作はブロック・ガウス消去と呼ばれ、\(A_{11}\) が正則であるため実行可能でありかつ一意である。
\(A_{11}\) を主座小行列として含む任意の部分行列は、(0.8.5.3) のブロック対角化を行う前後で行列式が変わらない。したがって、任意の添字集合 \(\beta=\{i_{1},\ldots,i_{m}\}\subseteq\{1,\ldots,n-k\}\) に対し、添字をシフトした集合 \(\tilde{\beta}=\{i_{1}+k,\ldots,i_{m}+k\}\) を定めると、
\(\det A[\alpha\cup\tilde{\beta},\,\alpha\cup\tilde{\gamma}]\)(ブロック消去前)\(=\det(A_{11}\oplus S[\beta,\gamma])\)(ブロック消去後)である。
したがって、
\det S[\beta,\gamma]
= \dfrac{\det A[\alpha\cup\tilde{\beta},\,\alpha\cup\tilde{\gamma}]}{\det A[\alpha]}
例えば、\(\beta=\{i\}\)、\(\gamma=\{j\}\) とし、\(\alpha=\{1,\ldots,k\}\) とすると、
\det S[\beta,\gamma]
= s_{ij}
= \dfrac{\det A[\{1,\ldots,k,k+i\},\,\{1,\ldots,k,k+j\}]}{\det A_{11}}
したがって、\(S\) の各成分は \(A\) の小行列式(小行列の行列式)の比として書ける。
(b) \(\mathrm{rank}\,A = \mathrm{rank}\,A_{11} + \mathrm{rank}\,S \ge \mathrm{rank}\,A_{11}\) が成り立つ。
また、\(\mathrm{rank}\,A = \mathrm{rank}\,A_{11}\) が成り立つための必要十分条件は、\(A_{22} = A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}\) である。
(c) \(A\) が正則であるための必要十分条件は \(S\) が正則であることである。
これは \(\det A = \det A_{11}\,\det S\) が成り立つためである。
したがって \(A\) が正則ならば \(\det S = \det A / \det A_{11}\) である。
Schur補行列と逆行列・余因子・階数1摂動に関する恒等式
A が正則であると仮定する。このとき、(0.8.5.3) の両辺を逆数(逆行列)に取ることで、(0.7.3.1) とは異なる形の逆行列の表現を得る:
A^{-1} =
\begin{bmatrix}
A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1} A_{12} S^{-1} A_{21} A_{11}^{-1}
&
- A_{11}^{-1} A_{12} S^{-1}
\\
- S^{-1} A_{21} A_{11}^{-1}
&
S^{-1}
\end{bmatrix}
ここから、部分行列 \(A^{-1}[\{k+1,\ldots,n\}]\) は \(S^{-1}\) に等しいことがわかる。したがって、
\det A^{-1}[\{k+1,\ldots,n\}]
= \dfrac{\det A_{11}}{\det A}
これは Jacobi の恒等式 (0.8.4.1) の一形態である。逆行列を余因子行列で表す別の形を用いると、
\det\!\bigl( (\operatorname{adj} A)[\{k+1,\ldots,n\}] \bigr)
= (\det A)^{\,n-k-1} \det A_{11}
\(\alpha^{c}\) が 1 要素のみからなるとき、\(A[\alpha]\) の Schur 補行列はスカラーとなり、(0.8.5.1) は次の恒等式に簡約される:
\det A
=
A[\alpha^{c}] \, \det A[\alpha]
-
A[\alpha^{c},\alpha] \,
(\operatorname{adj} A[\alpha]) \,
A[\alpha,\alpha^{c}]
この恒等式は \(A[\alpha]\) が特異であっても成立する。たとえば \(\alpha=\{1,\ldots,n-1\}\) とすると \(\alpha^{c}=\{n\}\) であり、行列 \(A\) は次の境界付き行列(縁取り行列)(bordered matrix)として表せる:
A =
\begin{bmatrix}
\tilde{A} & x \\
y^{\top} & a
\end{bmatrix}\\
\quad
\tilde{A}\in M_{n-1}(F),\;
x,y\in F^{\,n-1},\;
a\in F
このとき (0.8.5.9) は境界付き行列の Cauchy 展開を与える:
\det
\begin{bmatrix}
\tilde{A} & x \\
y^{\top} & a
\end{bmatrix}
=
a\,\det \tilde{A}
-
y^{\top} (\operatorname{adj}\tilde{A})\, x
Cauchy 展開 (0.8.5.10) は、\(\tilde{A}\) の余因子(符号付き小行列式、サイズ \(n-2\))と、1 行 1 列の双線形形式を含む。一方、Laplace 展開 (0.3.1.1) は \(A\) のサイズ \(n-1\) の符号付き小行列式と線形形式を含む。
もし \(a \neq 0\) であれば、行列 \([a]\) の Schur 補行列を用いて
\det
\begin{bmatrix}
\tilde{A} & x \\
y^{\top} & a
\end{bmatrix}
=
a \, \det(\tilde{A} - a^{-1} x y^{\top})
が得られる。この等式の右辺を (0.8.5.10) の右辺と等置し、さらに \(a=-1\) を代入すると、階数1摂動の Cauchy の公式を得る:
\det(\tilde{A} + x y^{\top})
=
\det \tilde{A}
+
y^{\top} (\operatorname{adj} \tilde{A})\, x
シューア補行列の商性質と行列式の恒等式
(a) で述べたシューア補集合の一意性は、シューア補集合をシューア補集合内に含める恒等行列を導くために用いることができる。
シューア補行列の一意性から導かれる「商性質(quotient property)」と、ブロック行列におけるいくつかの行列式恒等式について説明する。
まず、\( A_{11} \) が正則な \( k \times k \) ブロックであり、さらにこの \( A_{11} \) を 2×2 のブロックに再分割して、左上の \( \ell \times \ell \) ブロック \( \mathcal{D}_{11} \) が正則であるとする。
行列 \( A_{21} \) を \( A_{21} = [\mathcal{C}_{1}\; \mathcal{C}_{2}] \) と書き、ここで \(\mathcal{C}_{1} \) は \((n-k)\times \ell\) 行列とする。
さらに \( A_{12}^{\top} = [\mathcal{B}_{1}^{\top}\; \mathcal{B}_{2}^{\top} \) と分割し、\( \mathcal{B}_{1} \) は \( \ell \times (n-k) \) 行列とする。
このとき、次のように細分化されたブロック行列が得られる。
A =
\begin{bmatrix}
\mathcal{D}_{11} & \mathcal{D}_{12} & \mathcal{B}_{1} \\
\mathcal{D}_{21} & \mathcal{D}_{22} & \mathcal{B}_{2} \\
\mathcal{C}_{1} & \mathcal{C}_{2} & A_{22}
\end{bmatrix}
ここから、まず最初の \( \ell \) 行の線形結合を次の \( k - \ell \) 行に加えることで、\( \mathcal{D}_{21} \) を \(0\) ブロックに消去する。この操作は、前述の一意性により可能である。こうして得られる行列を次のように書く。
A' =
\begin{bmatrix}
\mathcal{D}_{11} & \mathcal{D}_{12} & \mathcal{B}_{1} \\
0 & A_{11}/\mathcal{D}_{11} & \mathcal{B}_{2}' \\
\mathcal{C}_{1} & \mathcal{C}_{2} & A_{22}
\end{bmatrix}
ここで、中央のブロック \( A_{11}/\mathcal{D}_{11} \) は、行列 \( A_{11} \) の中でさらに \( \mathcal{D}_{11} \) を消去したときに得られるシューア補行列であり、必ず正則となる。
次に、行列 \( A' \) の最初の \( k \) 行の線形結合を最後の \( n-k \) 行に加え、ブロック \([C_{1}\; C_{2}]\) を \(0\) ブロックに消去する。こうして得られる行列を
A'' =
\begin{bmatrix}
\mathcal{D}_{11} & \mathcal{D}_{12} & \mathcal{B}_{1} \\
0 & A_{11}/\mathcal{D}_{11} & \mathcal{B}_{2}' \\
0 & 0 & A/A_{11}
\end{bmatrix}
と書く。ここで右下のブロック \( A/A_{11} \) は、行列 \( A \) における \( A_{11} \) のシューア補行列となる。
また、行列 \( A/A_{11} \) の右下ブロックは、行列 \( A/A_{11} \) 内での \( A_{11}/\mathcal{D}_{11} \) のシューア補行列となる。
この観察により、シューア補行列の「商性質」が得られる:
A / A_{11}
= (A / \mathcal{D}_{11}) \, / \,(A_{11}/\mathcal{D}_{11})
次に、(0.8.5.3) の 4 つのブロック \( A_{ij} \) がすべて同じサイズの正方ブロックであり、かつ \( A_{11} \) が \( A_{21} \) と可換である場合を考える。
このときシューア補行列 \( S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \) を用いると、
\det A
= \det A_{11} \, \det S
= \det(A_{11} S)
となる。さらに、
\det (A_{11} S)
= \det (A_{11}A_{22} - A_{11}A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})
= \det (A_{11}A_{22} - A_{21}A_{12})
であるから、
\det A
= \det(A_{11}A_{22} - A_{21}A_{12})
同様に、\( A_{11} \) が \( A_{12} \) と可換である場合にも同じ結論が得られる。
また可換性を連続性の議論で拡張すれば、(0.8.5.13) は \( A_{11} \) が \( A_{21} \) または \( A_{12} \) のいずれかと可換であれば、たとえ \( A_{11} \) が特異であっても成立する。
さらに、\( A_{22} \) が \( A_{21} \) または \( A_{12} \) のいずれかと可換である場合には、\( A_{22} \) のシューア補行列を用いる同様の議論により、
\det A
= \det(A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21})
行列解析の総本山
総本山の目次📚

記号の意味🔎


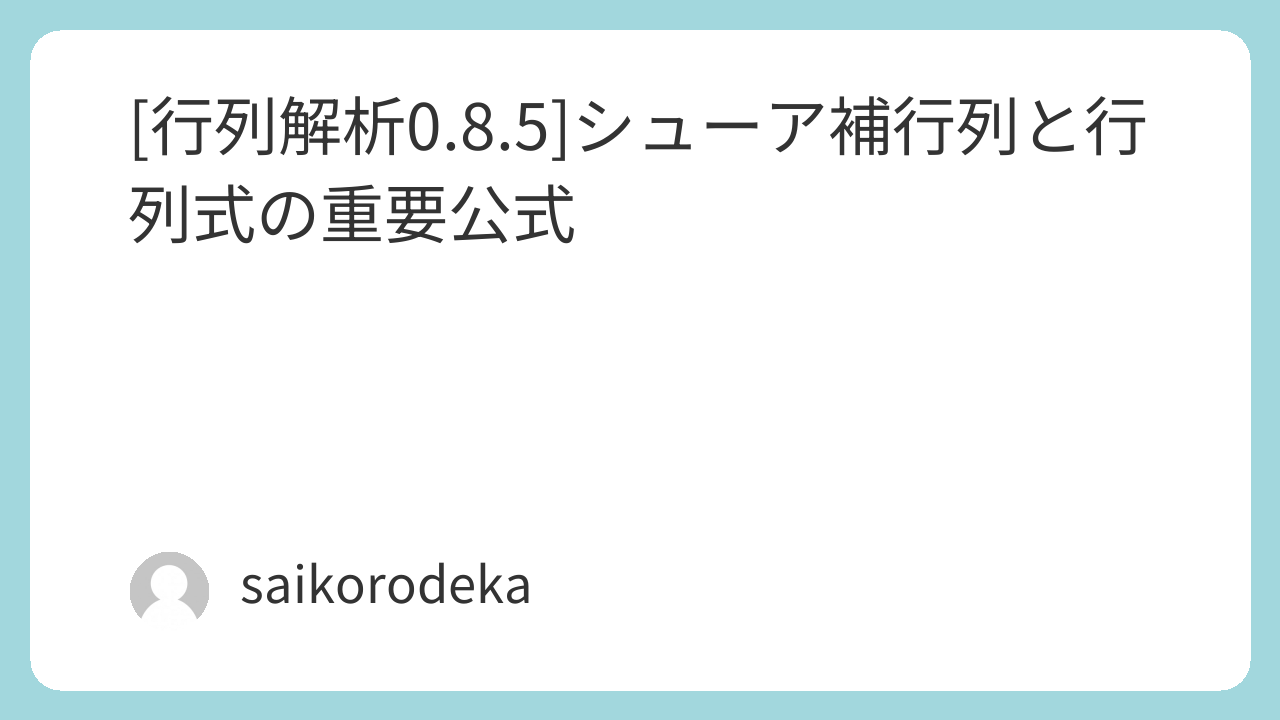

コメント