0.1.7 次元
ある正の整数 \( n \) が存在して、ベクトル空間 \( V \) のすべての基底がちょうど \( n \) 個の要素からなるとき、その \( n \) を \( V \) の次元(dimension)と呼び、記号 \( \dim V \) で表します。このとき \( V \) は有限次元です。そうでないときは無限次元です。
無限次元の場合でも、任意の2つの基底の間には1対1の対応があります。実数空間 \( \mathbb{R}^n \) の次元は \( n \)、複素数空間 \( \mathbb{C}^n \) の複素数体上での次元は \( n \)、実数体上での次元は \( 2n \) です。
ベクトル \( e_1, \ldots, e_n \) による標準基底(standard basis)は、各ベクトル \( e_i \) が \( i \) 番目の成分に 1 を持ち、他はすべて 0 である形の \( \mathbb{F}^n \) の基底です。
「\( V \) は \( n \) 次元のベクトル空間である」というのは、「\( V \) は有限次元であり、次元が \( n \) である」という意味の省略表現です。
有限次元ベクトル空間の任意の部分空間は有限次元であり、もし真部分空間であるならば次元は元の空間より小さくなります。
有限次元ベクトル空間 \( V \) において、部分空間 \( S_1 \)、\( S_2 \) が与えられたとき、次の関係が成り立ちます:
\begin{align}&\dim(S_1 \cap S_2) + \dim(S_1 + S_2) \notag \\
&= \dim S_1 + \dim S_2 \notag
\end{align}これを変形すると:
\begin{align}&\dim(S_1 \cap S_2) \notag \\
&= \dim S_1 + \dim S_2 - \dim(S_1 + S_2) \notag \\
&\ge \dim S_1 + \dim S_2 - \dim V \notag \\
\end{align}この不等式から、有用な事実が得られます。もし
\delta = \dim S_1 + \dim S_2 - \dim V \ge 1
であれば、交差部分 \( S_1 \cap S_2 \) の次元は少なくとも \( \delta \) であり、したがって少なくとも \( \delta \) 個の線形独立なベクトルを含みます。特に、ゼロでないベクトルが必ず存在します。
さらに帰納法を使うと、部分空間 \( S_1, \ldots, S_k \) に対して:
\begin{align}
\delta & = \dim S_1 + \cdots + \dim S_k - (k - 1)\dim V \ge 1 \notag
\end{align}
ならば、交差部分 \( S_1 \cap \cdots \cap S_k \) の次元は少なくとも \( \delta \) であり:
\dim(S_1 \cap \cdots \cap S_k) \ge \delta
ゆえに、非ゼロベクトルを含む線形独立なベクトルが \( \delta \) 個存在します。
行列解析の総本山
総本山の目次📚

記号の意味🔎


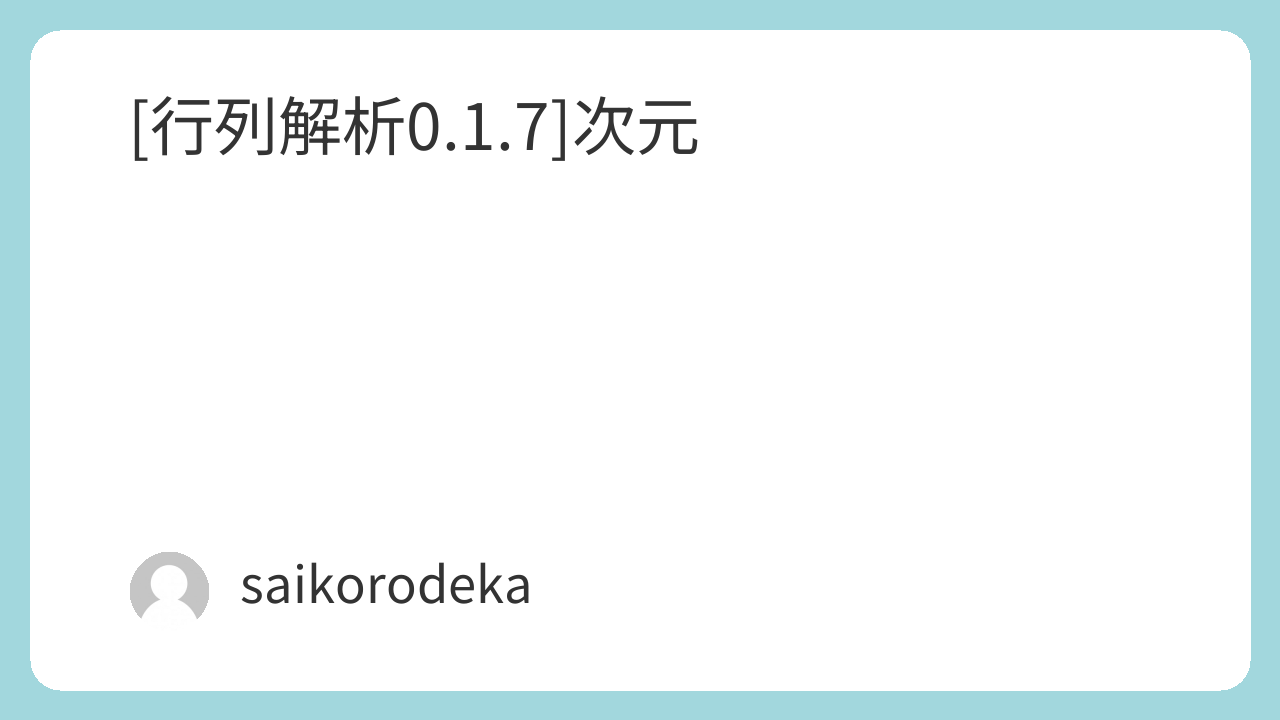

コメント