7.3.問題集
次の問題では、\( X \in M_{m,n} \) に対して、\( \sigma_1(X) \ge \cdots \ge \sigma_q(X) \) を \( X \) の特異値(大きい順に並んだもの)とし、\( q = \min\{m, n\} \) とする。
7.3.P1
行列 \( A \) の特異値が、極分解(7.3.1)における半正定値行列 \( P \) および \( Q \) の固有値であることを説明せよ。
7.3.P2
\( A, B \in M_n \) とする。極分解 \( A = P_1U_1 \)、\( B = P_2U_2 \) が与えられているとき、\( A \) と \( B \) がユニタリ同値であるのは、\( P_1 \) と \( P_2 \) がユニタリ相似である場合に限ることを示せ。
7.3.P3
\( A \in M_n \) が零の特異値をもつことと、零の固有値をもつことが同値であることを示せ。
7.3.P4
\( A \in M_{m,n} \) とし、次のような特異値分解をもつとする:
A = V \Sigma W^{*}
ここで、\(\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_q)\) であり、\( V = [v_1, \ldots, v_m] \)、\( W = [w_1, \ldots, w_n] \) と分割する。
(a) 各 \( k = 1, \ldots, q \) に対して次を示せ:
A^{*} v_k = \sigma_k w_k, \quad A w_k = \sigma_k v_k, \quad v_k^{*} A w_k = \sigma_k
単位ベクトル \( w_k \) は \( A \) の(右)特異ベクトルであり、単位ベクトル \( v_k \) は \( A \) の左特異ベクトルである。
(b) \( i \in \{1, \ldots, q\} \) に対して、次の関係を示せ:
\max\{\|A x\|_2 : x \in \mathrm{span}\{w_i, \ldots, w_n\}, \|x\|_2 = 1\} = \sigma_i
= \min\{\|A x\|_2 : x \in \mathrm{span}\{w_1, \ldots, w_i\}, \|x\|_2 = 1\}
7.3.P5
\( A, E \in M_{m,n} \)、\( k \in \{1, \ldots, q\} \) とする。ここで、\( \sigma_k \) は \( A \) の単純な非零特異値であり、単位特異ベクトル \( v_k, w_k \) が次を満たすとする:
A v_k = \sigma_k w_k
(a) 次の行列
\begin{bmatrix}
0 & A \\
A^{*} & 0
\end{bmatrix}
が固有値 \( \sigma_k \) をもつことを示せ。このとき対応する固有ベクトルは
x = \begin{bmatrix} v_k \\ w_k \end{bmatrix}
である。
(b) 式 (6.3.12) を用いて、次を示せ:
\frac{d}{dt} \sigma_k(A + tE) \big|_{t=0} = \mathrm{Re}\, (v_k^{*} E w_k)
7.3.P6
\( B \in M_n(\mathbb{R}) \) とし、任意の \( t \in \mathbb{R} \) に対して
A(t) =
\begin{bmatrix}
B & x \\
y^{*} & t
\end{bmatrix}
\in M_{n+1}(\mathbb{R})
と定める。ただし、\( B, x, y \) のうち少なくとも1つは零でないものとする。さらに
\mu = \max\{\sigma_1\!\left(
\begin{bmatrix}
B \\[3pt]
y^{*}
\end{bmatrix}
\right),
\sigma_1([B \; x])\}
とおく。
(a) すべての \( t \) に対して \( \sigma_1(A(t)) \ge \mu \gt 0 \) が成り立つこと、またある \( t_0 \in \mathbb{R} \) が存在して
\sigma_1(A(t_0)) = \min_{t \in \mathbb{R}} \sigma_1(A(t)) \gt 0
となることを説明せよ。
(b) \( \sigma_1(A(t_0)) \) が \( A(t_0) \) の単純な特異値でない場合、なぜ \( \mu = \sigma_1(A(t_0)) \) となるのかを説明せよ。
(c) \( \sigma_1(A(t_0)) \) が \( A(t_0) \) の単純な特異値である場合、式 (7.3.12) を用いて \( \mu = \sigma_1(A(t_0)) \) であることを示せ。
7.3.P7
\( A \in M_{m,n} \) とし、特異値分解 \( A = V \Sigma W^{*} \) をもつとする。次のように定める:
A^{\dagger} = W \Sigma^{\dagger} V^{*}
ここで、\( \Sigma^{\dagger} \) は \(\Sigma\) の非零特異値をその逆数に置き換えた後に転置したものである。次を示せ:
(a) \( AA^{\dagger} \) および \( A^{\dagger}A \) はエルミートである。
(b) \( AA^{\dagger}A = A \)。
(c) \( A^{\dagger}AA^{\dagger} = A^{\dagger} \)。
(d) \( A \) が正方かつ正則なら \( A^{\dagger} = A^{-1} \)。
(e) \( (A^{\dagger})^{\dagger} = A \)。
(f) \( A^{\dagger} \) は (a)–(c) の性質により一意に定まる。
この \( A^{\dagger} \) は Moore–Penrose一般化逆行列 と呼ばれる。別の方法として、\( A^{\dagger} \) の特異値分解を書き下し、その3つの因子が (a)–(c) によって一意に決まることを示してもよい。
7.3.P8
本問題は (7.1.P28) の続きであり、同じ記号を用いる。
(a) 前問の恒等式 (a)–(c) を用いて、\( C = BX \) を満たす任意の \( X \) に対して
X^{*} B X = C^{*} B^{\dagger} C
が成り立つことを示せ。
(b) 半正定値行列
A =
\begin{bmatrix}
B & C \\
C^{*} & D
\end{bmatrix}
が \( B \oplus (D - C^{*}B^{\dagger}C) \) に ∗合同(star-congruent)であることを示せ。
(c) \( B \) が正則の場合、\( D - C^{*}B^{\dagger}C = D - C^{*}B^{-1}C \) となることを説明せよ。
(d) \( D - C^{*}B^{\dagger}C \) を、\( A \) における \( B \) の一般化されたSchur補行列とみなすことの妥当性について論ぜよ。
7.3.P9
線形方程式 \( A x = b \) の最小二乗解とは、\( \|x\|_2 \) が最小で、かつ \( \|A x - b\|_2 \) が最小となるようなベクトル \( x \) のことである。\( x = A^{\dagger} b \) が \( A x = b \) の一意な最小二乗解であることを示せ。
7.3.P10
\( A \in M_{m,n} \) の特異値分解 \( A = V \Sigma W^{*} \) に対して、\( r = \mathrm{rank}(A) \) とする。このとき次を示せ:
(a) \( W \) の最後の \( n - r \) 列は \( A \) の零空間の直交基底である。
(b) \( V \) の最初の \( r \) 列は \( A \) の値域の直交基底である。
(c) \( V \) の最後の \( n - r \) 列は \( A^{*} \) の零空間の直交基底である。
(d) \( W \) の最初の \( r \) 列は \( A^{*} \) の値域の直交基底である。
以下では、特異値分解(Singular Value Decomposition; SVD)および関連する性質や不等式についての演習問題を扱う。
7.3.P11
\( A \in M_{m,n} \) とする。次を示せ:
\sigma_{1}(A) = \max \{ |x^{*} A y| : x \in \mathbb{C}^{m},\ y \in \mathbb{C}^{n},\ \|x\|_{2} = \|y\|_{2} = 1 \}.
7.3.P12
\( A \in M_{m,n} \)、\( B \in M_{p,n} \) とし、
C =
\begin{bmatrix}
A \\
B
\end{bmatrix}
\in M_{m+p,n}
とおく。\( \operatorname{rank} C = r \) とし、特異値分解 \( C = V \Sigma W^{*} \) が与えられているとする。このとき、\( W \) の最後の \( n - r \) 列は、\( A \) および \( B \) の零空間の共通部分の正規直交基底を成すことを示せ。また、SVDを用いて \( \operatorname{range}(A) + \operatorname{range}(B) \) の正規直交基底を得る方法を説明せよ。
7.3.P13
極分解(polar decomposition)(7.3.1) から特異値分解 (2.6.3) を導出せよ。
7.3.P14
\( A \in M_{n} \) とする。\( A \) が相似変換により対角化可能であることと、正定値エルミート行列 \( P \) が存在して \( P^{-1} A P \) が正規行列となることは同値であることを示せ。
7.3.P15
\( A \in M_{m,n} \) とする。このとき次を示せ:
A^{\dagger} = \lim_{t \to 0} \left( A^{*}(A A^{*} + tI)^{-1} \right).
7.3.P16
\( A, B \in M_{m,n} \) とする。特異値に関する基本的不等式として次が成り立つ:
\sigma_{i+j-1}(A + B) \le \sigma_{i}(A) + \sigma_{j}(B)
\quad \text{if } 1 \le i, j \le q \text{ and } i + j \le q + 1,
\sigma_{i+j-1}(A B^{*}) \le \sigma_{i}(A)\sigma_{j}(B)
\quad \text{if } 1 \le i, j \le q \text{ and } i + j \le q + 1.
(a) (7.3.13) を証明するために、(7.3.4) で定義されるようなエルミートブロック行列 \( A, B \in M_{m+n} \) を考える。このとき、特異値と固有値の関係
\sigma_{k}(A) = \lambda_{m+n-k+1}(A)
が任意の \( k \in \{1, \dots, q\} \) について成立することを説明せよ。この恒等式およびWeylの不等式 (4.3.1) から (7.3.13) を導け。
(b) (7.3.13) から \( \sigma_{1}(A + B) \le \sigma_{1}(A) + \sigma_{1}(B) \) が従うことを示せ。なぜこれは当然の結果といえるか。
(c) \( i > 1 \) のとき、不等式 \( \sigma_{i}(A + B) \le \sigma_{i}(A) + \sigma_{i}(B) \) が必ずしも成立しないことを例を挙げて示せ。
(d) 摂動評価式を証明せよ:
|\sigma_{i}(A + B) - \sigma_{i}(A)| \le \sigma_{1}(B)
\quad \text{for any } i \in \{1, \dots, q\}.
(f) (7.3.14) から \( \sigma_{1}(A B^{*}) \le \sigma_{1}(A)\sigma_{1}(B) \) が従うことを示せ。なぜこれも当然の結果といえるか。また、極分解、部分空間の交わり、(7.3.P4(b))、および (7.3.8) のみを用いた (7.3.14) の証明については Horn and Johnson (1991) の定理 3.3.16 を参照せよ。
7.3.P17
\( A \in M_{n} \) の固有値を絶対値の大きい順に並べて \( |\lambda_{1}(A)| \ge \cdots \ge |\lambda_{n}(A)| \) とする。
(a) H. Weyl(1949)による次の不等式は、固有値の絶対値と特異値の間の乗法的メジャライゼーションを表す:
|\lambda_{1} \cdots \lambda_{k}| \le \sigma_{1} \cdots \sigma_{k}
\quad (k = 1, \dots, n),
ただし \( k = n \) の場合には等号が成立する。この証明は Horn and Johnson (1991) の定理 3.3.2 を参照せよ(別証明は (5.6.P57) を参照)。特に \( k = 1 \) および \( k = n \) の場合において、なぜWeylの積の不等式が成り立つのかを説明せよ。
(b) 乗法的不等式 (7.3.16) から、次の加法的不等式が導かれる:
|\lambda_{1}| + \cdots + |\lambda_{k}| \le \sigma_{1} + \cdots + \sigma_{k}
\quad (k = 1, \dots, n).
その証明は Horn and Johnson (1991) の定理 3.3.13 を参照せよ。また、(7.3.15) の不等式が、\( A \) の固有値の絶対値と特異値の間の厳密なメジャライゼーション関係ではない理由を説明せよ。
7.3.P18
不等式 (7.3.17) の場合 k = n は、既存の道具を用いて、積の不等式 (7.3.16) に頼らずに扱うことができる。前問の表記を採用して詳細を示せ。
(a) \( A = U T U^{*} \) とし、ここで \( T = [t_{ij}] \) は上三角行列で各 \( t_{ii} = \lambda_i \) とする。このとき、対角ユニタリ行列 \( D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n) \) が存在して各 \( d_i t_{ii} = |\lambda_i| \) となる理由を説明せよ。
(b) \( D T = V \Sigma W^{*} \) とし、ここで \( V = [v_1, \dots, v_n] \)、\( W = [w_1, \dots, w_n] \) はユニタリ、\( \Sigma = \mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n) \)、かつ \( s_1 \ge \dots \ge s_n \ge 0 \) とする。なぜ各 \( s_j = \sigma_j \) となるのか説明せよ。
(c) 以下の関係を説明せよ:
\sum_j |\lambda_j| = \mathrm{tr}(D T) = \mathrm{tr}\Big(\sum_j \sigma_j v_j w_j^*\Big) = \Big|\sum_j \sigma_j w_j^* v_j\Big| \le \sum_j \sigma_j,
等号成立は、各 \( j \) に対して \( \sigma_j \neq 0 \) のとき \( w_j = e^{i \theta_j} v_j \) である場合に限られる。
(d) これにより、対角ユニタリ行列 \( E \) が存在して \( V \Sigma W^{*} = V \Sigma E V^{*} \) となることが従う。
(e) \( D T \) が正規行列である理由を説明せよ。結論として、\( T \) は対角行列であり、\( A \) は正規行列である。
(f) これにより次の不等式が成立する:
|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \le \sigma_1 + \dots + \sigma_n
等号成立は、かつて \( A \) が正規行列である場合に限られる。
(g) 次の不等式も成立する:
| \mathrm{tr} A | \le \sigma_1 + \dots + \sigma_n
等号成立は、かつて \( A \) がエルミートかつ半正定値である場合に限られる。
7.3.P19
\( A, B \in M_n \) とする。
(a) \( AB \) と \( BA \) は固有値を共有するが、行列
\begin{bmatrix}0 & 1 \\ 0 & 0\end{bmatrix}, \quad
\begin{bmatrix}0 & 0 \\ 0 & 1\end{bmatrix}
を考慮すると、なぜ \( AB \) と \( BA \) が必ずしも同じ特異値を持つとは限らないか説明せよ。
(b) なぜ \( AB \) と \( B^{*} A^{*} \) は同じ特異値を持つのか説明せよ。
(c) \( A \) と \( B \) がエルミートである場合、\( AB \) と \( BA \) は同じ特異値を持つことを示せ。
(d) \( A \) と \( B \) が正規行列である場合、\( AB \) と \( BA \) は同じ特異値を持つことを示せ。
7.3.P20
\( A \in M_{m,n} \) とし、行列 (7.3.4) を用いる。\( v \in \mathbb{C}^{n} \) で \( Av \neq 0 \) とする。次を定義する:
u = \frac{Av}{\|Av\|_2}, \quad
y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}
このとき、\( y^{*} A y = \|Av\|_2 \) を示し、さらに上限 (6.3.17) を \( A \) と \( y \) に対して計算せよ。結論として、\( A \) には少なくとも1つの特異値が次の実数区間に存在する:
\left\{ t \in \mathbb{R} :
\begin{aligned}
& |t - \|Av\|_2| \\
& \le \frac{1}{\sqrt{2}} \left\| A^* u - \|Av\|_2 v \right\|_2 \\
& = \frac{1}{\sqrt{2}} \|Av\|_2 \:\left\| (A^*A - \|Av\|_2^2 I) v \right\|_2
\end{aligned}
\right\}
7.3.P21
式 (7.3.15) を用いて、行列への「小さい」摂動がそのランクを減少させることはできないが、増加させることはあり得る理由を説明せよ。「小さい」とはどの程度かも考察せよ。
7.3.P22
\( A, B \in M_{m,n} \) がユニタリ等価であることと、次の条件は同値であることを示せ:
\mathrm{tr}\big((A^{*}A)^k\big) = \mathrm{tr}\big((B^{*}B)^k\big), \\
\quad k=1,\dots,n
もし \( m = n \) の場合、この条件と (2.2.8) の条件を比較せよ。後者は \( A \) と \( B \) がユニタリ相似かを判定するために必要かつ十分な条件である。
7.3.P23
\( A, B \in M_n \) とする。
(a) \( AA^{*} = BB^{*} \) であることと、ユニタリ行列 \( U \) が存在して \( A = BU \) となることは同値であることを示せ。
(b) \( A \) が正則で、\( A = BU \) かつ \( U \) がユニタリのとき、\( A \bar{A} = B \bar{B} \) は \( A = U^T B \) と同値であることを示せ。
(c) \( A \) と \( B \) が正則で、かつ \( AA^{*} = BB^{*} \) および \( A \bar{A} = B \bar{B} \) の場合、\( A^T \bar{A} = B^T \bar{B} \) となることを示せ。
(d) \( x = [1, 1]^T \), \( y = [1, -1]^T \)、次の行列を考える:
A = \begin{bmatrix} 0 & x^T \\ 0_{2,1} & 0_2 \end{bmatrix}, \quad
B = \begin{bmatrix} 0 & y^T \\ 0_{2,1} & 0_2 \end{bmatrix}
正則性の仮定を除くと、(c) の含意が必ずしも成立しない理由を説明せよ。
(e) ブロック行列 \( K_A, K_B \in M_{4n} \) を、(4.4.32) の 2,4 ブロックを零行列で置き換えて構成する。\( A \) と \( B \) が正則なら、(4.4.P46) を用いて、\( A \) と \( B \) がユニタリ合同であることと、\( K_A \) と \( K_B \) がユニタリ相似であることが同値であることを示せ。
7.3.P24
\( A, B \in M_{m,n} \) について、次の条件は同値であることを示せ:
A \text{ と } B \text{ はユニタリ等価 } \\
\iff \\
\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{bmatrix} \text{ と }
\begin{bmatrix} 0 & B \\ B^* & 0 \end{bmatrix} \text{ がユニタリ相似 }
7.3.P25
\( A = [a_{ij}] \in M_n \) およびユニタリ行列 \( U \in M_n \) とする。
(a) 次を示せ:
|\mathrm{tr}(UA)| \le \sum_{i,j} |a_{ij}|
(b) 次を示せ:
\sigma_1 + \cdots + \sigma_n \le \sum_{i,j} |a_{ij}|
この結果を (2.3.P14) と比較せよ。
7.3.P26
\( A \in M_2 \) がエルミートかつ半正定値、非零であるとする。\( \tau = \sqrt{\mathrm{tr} A + 2\sqrt{\det A}} \) とする。
(a) 次を示せ:
A^{1/2} = \tau^{-1} \left( A + \sqrt{\det A} \, I_2 \right)
(b) この表現を用いて、(7.2.6) の後の演習で平方根を計算せよ。
7.3.P27
\( A \in M_2 \) が非零とし、極分解 \( A = PU \) および \( A = VQ \) が存在するとする。ここで \( P, Q \) は半正定値(かつ一意に決定される)である。次を定義する:
s = \sqrt{\|A\|_2^2 + 2|\det A|}
次を示せ:
P = s^{-1} (AA^* + |\det A| I_2), \quad
Q = s^{-1} (A^* A + |\det A| I_2)
\( A \) が実行列であれば、\( P \) と \( Q \) も実行列であることに注意せよ。
7.3.P28
\( A \in M_2 \) が非零、任意の実数 \( \theta \) で \( \det A = e^{i\theta} |\det A| \) とする。次を定義する:
Z_\theta = A + e^{i\theta} \operatorname{adj}(A^*), \quad
\delta = |\det Z_\theta|
(a) \( \delta = (\sigma_1 + \sigma_2)^2 \neq 0 \) を示せ。
(b) 次を示せ:
U = \delta^{-1/2} (A + e^{i\theta} \operatorname{adj}(A^*))
\( U \) はユニタリであり、かつ \( U^* A \) と \( A U^* \) は半正定値である。
(c) 前問で決定された半正定値行列 \( P \) と \( Q \) を用いて、\( A = PU = UQ \) が極分解である理由を説明せよ。
(d) \( A \) が実行列である場合、\( U \) は実行列として選べる理由を説明せよ。
7.3.P29
前の二つの問題を用いて、次の行列の左・右極分解を計算せよ:
A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}
7.3.P30
\( A \in M_n \) が非特異行列の場合、なぜ \( A^{-1} \) の特異値は次のように順序付けられるのか説明せよ:
\sigma_n^{-1} \ge \cdots \ge \sigma_1^{-1}
7.3.P31
\( A \in M_n \) がユニタリ行列のスカラー倍であるのは、かつそのときに限り、特異値がすべて等しい(\( \sigma_1 = \cdots = \sigma_n \))ことを示せ。
7.3.P32
\( A \in M_{n,m} \) で rank \( A = r \) とする。
(a) 7.3.2(a) の thin 特異値分解を用いて、次の形で full-rank 分解を与えよ:
A = X Y^*, \quad X \in M_{n,r}, \, Y \in M_{m,r}, \, \mathrm{rank}\, X = \mathrm{rank}\, Y = r
(b) \( A \) の r 個の一次独立な行と r 個の一次独立な列が交わる部分行列 \( B \) を考える。full-rank 分解 \( A = XY^* \) を用いて、\( B \) が非特異であることを示せ。
7.3.P33
\( A \in M_{n,m} \) で \( n \ge m \) とし、\( P = (A^* A)^{1/2} = W \Sigma W^* \in M_m \) とする。(7.3.1) を用いて、正規直交列を持つ \( V \in M_{n,m} \) が存在し、\( A = V \Sigma W^* \) となることを示せ。\( n \lt m \) の場合はどうなるか?
7.3.P34
(7.2.9) で QR 分解から Cholesky 分解を導出した。同様に (7.3.12) を用いて、Cholesky 分解から QR 分解を導出せよ。
7.3.P35
\( A \in M_n \) で極分解 \( A = PU \) を持つとする。\( A \) が正規であることと \( PU = UP \) が成立することは同値であることを示せ。
7.3.P36
\( A \in M_n \) が正規で、その特異値がすべて異なるとする。
(a) \(A\)の固有値について何が言えるか。
(b) \(A^∗A\)が実数ならば、\(A\)が対称分布であることを示せ。
7.3.P37
\( A, B \in M_n \) がエルミートで相似:\( A = SBS^{-1} \) とする。\( S = UQ \) が極分解である場合、\( A \) と \( B \) はユニタリ相似であることを示せ。
7.3.P38
\( V, W \in M_n \) がユニタリかつ ∗合同:\( V = SBS^* \) とする。\( S = PU \) が極分解である場合、\( V \) と \( W \) は \( U \) を用いてユニタリ相似であることを示せ。
7.3.P39
\( \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_r) \) および \( M = \mathrm{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_r) \) とする。ただし \( |\lambda_i| = |\mu_i| = 1 \)(\( i = 1, \ldots, r \))。\( D = \Lambda \oplus 0_{n-r} \), \( E = M \oplus 0_{n-r} \) とする。また \( S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \in M_n \) は非特異で、\( D = S E S^* \) とする。
(a) \( S_{11} \) は非特異であり、かつ \( \Lambda = S_{11} M S_{11}^* \) であることを示せ。
(b) \( P \in M_r \) を置換行列とすると、\( D = P M P^T \) となることを示せ。
7.3.P40
\( A \in M_n \) が rank \( A = r \) で、対角行列 \( D = \Lambda \oplus 0_{n-r} \) および \( E = M \oplus 0_{n-r} \) に ∗合同であるとする(ここで \( \Lambda \) と \( M \) はユニタリ)。
このとき、\( \Lambda \) と \( M \) は置換相似であることを示せ。
(4.5) の ∗合同標準形の議論(特に ∗合同で対角行列への特例 (4.5.24))を参照し、なぜこれが驚くべきことではないかを説明せよ。
7.3.P41
\( A, B \in M_n \) を正規行列とする。\( A \) が \( B \) に ∗合同であるのは、かつそのときに限り、rank \( A = \) rank \( B \) であり、複素平面上の原点から放射状に伸びる任意の線上に、\( A \) と \( B \) の非零固有値が同じ個数存在する場合であることを示せ。
7.3.P42
\( A \in M_{m,n} \) とし、\( q = \min\{m,n\} \)、さらに
A = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{r,s}
とする。また \( t = \min\{r,s\} \) とする。なぜ \( A \) の特異値は \( \sigma_1(A), \ldots, \sigma_q(A) \) と \( t-q \) 個のゼロ特異値からなるのか説明せよ。
7.3.P43
\( \| \cdot \| \) を \( M_n \) 上のユニタリ不変ノルムとする。もし \( A, B \in M_n \)、\( A \) が正規行列、\( B \) がエルミート行列であるなら、次を示せ:
\| AB \| = \| BA \|
この結果を (5.6.P58(b)) と比較せよ。
7.3.P44
\( A \in M_{m,n} \) とし、\( \hat{A} \in M_{r,s} \) を \( A \) の一部の行や列を削除して得られる部分行列とする。\( p = m - r + n - s \) とする。任意の \( X \in M_{k,l} \) に対して、特異値を非増加順に \( \sigma_1(X) \ge \sigma_2(X) \ge \cdots \) と定義し、\( i > \min\{k,l\} \) の場合は \( \sigma_i(X) = 0 \) とする。すると (7.3.6) から次が導かれる:
\sigma_i(A) \ge \sigma_i(\hat{A}) \ge \sigma_{i+p}(A), \quad 1 \le i \le \min\{r,s\}
7.3.P45
\( A, B \in M_n \) とする。次の主張を示せ:\( A \) は \( B \) にユニタリ相似であるのは、非特異行列 \( S \in M_n \) が存在して \( A = SBS^{-1} \) かつ \( A^* = SB^*S^{-1} \) となる場合に限る。
(a) \( A (S S^*) = (S S^*) A \) を示せ。
(b) \( S = PU \) を極分解とし、正定値行列 \( P \) が \( SS^* \) の多項式で表されるとする。なぜ \( AP = PA \) となるか説明せよ。
(c) これにより \( B = S^{-1} A S = U^* A U \) となることを結論せよ。
(d) この議論を (2.5.21) の証明と比較せよ。
参考文献・補足
(7.3.3) の実行列の場合は、C. Jordan により 1874 年に公表された。
いくつかの著者は (7.3.4) におけるエルミート行列を Wielandt 行列と呼ぶ。
(7.3.14) の追加応用例および歴史的概観については、R. A. Horn および I. Olkin, "When does A∗A = B∗B and why does one want to know?", Amer. Math. Monthly 103 (1996) 470–482 を参照。
問題 (7.3.P26〜28) は 2×2 行列の明示的極分解を提供する。
また、フロベニウス同伴行列の明示的極分解も存在する(P. van den Driessche, H. K. Wimmer, "Explicit polar decompositions of companion matrices", Electron. J. Linear Algebra 1 (1996) 64–69)。
問題 (7.3.P28) および 3×3 以上の行列への一般化は、R. A. Horn, G. Piazza, T. Politi, "Explicit polar decompositions of complex matrices", Electron. J. Linear Algebra 18 (2009) 693–699 で議論されている。
行列解析の総本山
総本山の目次📚
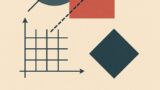
記号の意味🔎




コメント