2.3.6 定理:可換族の同時準三角化
前節の定理には、可換族に対応するバージョンがあります。すなわち、実数値行列の可換族は、ひとつの実数または実直交の類似変換によって、同時に共通の上準三角形形式に変換することができます。
(2.3.5) のブロック構造は、以下のような準対角行列 \( D = J_{n_1} \oplus \cdots \oplus J_{n_m} \in M_n \) に従って分割されていると考えると便利です。ここで \( J_k \) は \( k \times k \) の全ての成分が1の行列(0.2.8)を表し、各 \( n_j \) は1または2です。
定理 2.3.6
\( F \subseteq M_n(\mathbb{R}) \) を空でない可換族とする。
(a)
ある正則行列 \( S \in M_n(\mathbb{R}) \) および準対角行列 \( D = J_{n_1} \oplus \cdots \oplus J_{n_m} \in M_n \) が存在して、以下を満たす:
- (i) 各 \( A \in F \) に対して、\( S^{-1} A S \) は次の形式の実数上準三角行列であり、かつ \( D \) に準拠した形で分割されている: [ディスプレイ数式]
\begin{bmatrix} A_1(A) & * & \cdots & * \\ 0 & A_2(A) & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & A_m(A) \end{bmatrix} - (ii) \( n_j = 2 \) のとき、各 \( A \in F \) に対して \( A_j(A) \in M_2(\mathbb{R}) \) は以下の形になる: [ディスプレイ数式]
A_j(A) = \begin{bmatrix} a_j(A) & b_j(A) \\ -b_j(A) & a_j(A) \end{bmatrix} このとき、\( a_j(A) \pm i b_j(A) \) は \( A \) の固有値となる。
- (iii) \( n_j = 2 \) となる任意の \( j \in \{1, \ldots, m\} \) に対して、ある \( A \in F \) が存在し \( b_j(A) \ne 0 \) を満たす。
すべての \( A \in F \) が実固有値しか持たないならば、各 \( S^{-1} A S \) は上三角行列になる。
(b)
ある実直交行列 \( Q \in M_n(\mathbb{R}) \) および準対角行列 \( D = J_{n_1} \oplus \cdots \oplus J_{n_m} \in M_n \) が存在して、以下を満たす:
- (i) 各 \( A \in F \) に対して、\( Q^T A Q \) は上準三角行列 (2.3.6.1) の形式をとり、かつ \( D \) に準拠して分割される。
- (ii) \( n_j = 2 \) となる任意の \( j \in \{1, \ldots, m\} \) に対して、ある \( A \in F \) が存在し、\( A_j(A) \) は共役な非実固有値の対を持つ。
すべての \( A \in F \) が実固有値しか持たないならば、各 \( Q^T A Q \) は上三角行列になる。
証明
(a)
(2.3.3) の証明における帰納的パターンに従えば、各 \( A \in F \) に同じ方法で作用する正則実行列を構成すればよい。まず (1.3.19) により、すべての \( A \in F \) の共通ユニット固有ベクトル \( x \in \mathbb{C}^n \) を取る。これを \( x = u + iv \)(\( u, v \in \mathbb{R}^n \))と表す。
このとき、次の2つの可能性がある:
- {u, v} が一次従属:この場合、実ユニットベクトル \( w \in \mathbb{R}^n \) と実数スカラー \( \alpha, \beta \)(どちらもゼロではない)により、\( u = \alpha w, v = \beta w \) と書ける。すると \( x = (\alpha + i\beta)w \) となり、\( w = (\alpha + i\beta)^{-1}x \) はすべての \( A \in F \) の実ユニット固有ベクトルである。これにより、実直交行列 \( Q \) を \( w \) を最初の列として構成すれば、各 \( A \in F \) に対して次の形になる: [ディスプレイ数式]
Q^T A Q = \begin{bmatrix} \lambda(A) & * \\ 0 & * \end{bmatrix} ここで \( \lambda(A) \) は実固有値である。
- {u, v} が一次独立:このとき、(1.3.P3) により、実正則行列 \( S \) を構成して各 \( A \in F \) に対して [ディスプレイ数式]
S^{-1} A S = \begin{bmatrix} A_1(A) & * \\ 0 & * \end{bmatrix} の形式とでき、ここで \( A_1(A) \) は (2.3.6.2) の形になる。 もし \( b_1(A) \ne 0 \) ならば、\( a_1(A) \pm i b_1(A) \) は非実の共役固有値のペアである。 逆に、すべての \( A \in F \) に対して \( b_1(A) = 0 \)(つまりすべて実固有値)の場合、2×2ブロックは2つの1×1ブロックに分割される。
(b)
(a) で得られた正則実行列 \( S \) をQR分解(2.1.14)して \( S = QR \) とする。同様にして、(2.3.4) の証明に従えば、直交行列 \( Q \) は所望の性質を満たす。
(2.3.3) と同様に、上記の定理に現れる対角ブロックに対応する固有値の出現順序を制御することはできません。共通の固有ベクトル((1.3.19) により保証される)に従って、与えられた順序で固有値を受け入れる必要があります。
練習問題
- 行列 \( A \in \mathbb{M}_n \) に対して、\( A \bar{A} \) が実数行列であることと \( A \) が \( \bar{A} \) と可換であることが同値である理由を説明せよ。
- \( A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \) のとき、\( A \bar{A} \) が実数行列であること、および \( \operatorname{Re} A \) と \( \operatorname{Im} A \) が可換であることを示せ。
- \( A \in \mathbb{M}_n \) とし、\( A = B + iC \)(ただし \( B \) および \( C \) は実数行列)と表されているとする。このとき、\( A \bar{A} = \bar{A} A \) が成り立つことと \( BC = CB \) が成り立つことが同値であることを示せ。
\( A \bar{A} = \bar{A} A \) を満たす行列全体の集合 \( S = \{ A \in \mathbb{M}_n : A \bar{A} = \bar{A} A \} \) は、実行列全体の集合 \( \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \) よりも広い集合ですが、共通の重要な性質を持ちます。それは、任意の実正方行列が実直交類似によって実上準三角行列に変換できるように、集合 \( S \) に属する任意の行列も実直交類似によって複素上準三角行列に変換できるということです。
系 2.3.7
\( A \in \mathbb{M}_n \) とし、\( A \bar{A} = \bar{A} A \) が成り立っていると仮定します。このとき、実直交行列 \( Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \) と、準対角行列 \( D = J_{n_1} \oplus \cdots \oplus J_{n_m} \in \mathbb{M}_n \) が存在して、\( Q^T A Q \in \mathbb{M}_n \) は (2.3.6.1) 形式の複素上準三角行列であり、\( D \) に対応した形に分割され、次の性質を持ちます:
\( j \in \{1, \dots, m\} \) で \( n_j = 2 \) のとき、\( \operatorname{Re} A_j \) または \( \operatorname{Im} A_j \) の少なくとも一方が非実数の共役な固有値の対を持ちます。もし \( \operatorname{Re} A \) および \( \operatorname{Im} A \) が共に実固有値しか持たない場合、\( Q^T A Q \in \mathbb{M}_n \) は上三角行列となります。
証明
\( A = B + iC \) と書き、\( B \) および \( C \) は実行列とします。仮定と前の練習問題から、\( B \) と \( C \) は可換であることがわかります。(2.3.6b) より、実直交行列 \( Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \) と準対角行列 \( D = J_{n_1} \oplus \cdots \oplus J_{n_m} \in \mathbb{M}_n \) が存在して、
Q^T B Q, \quad Q^T C Q
のそれぞれが (2.3.6.1) 形式の実上準三角行列となり、\( D \) に対応して分割されています。さらに、\( j \in \{1, \dots, m\} \) で \( n_j = 2 \) のとき、\( A_j(B) \) または \( A_j(C) \) の少なくとも一方は非実数の共役な固有値の対を持ちます。したがって、
Q^T A Q = Q^T (B + iC) Q = Q^T B Q + i Q^T C Q
は、\( D \) に対応して分割された複素上準三角行列となります。もし \( B \) および \( C \) が共に実固有値のみを持つならば、すべての \( n_j = 1 \) であり、\( Q^T B Q \) および \( Q^T C Q \) は上三角行列となります。

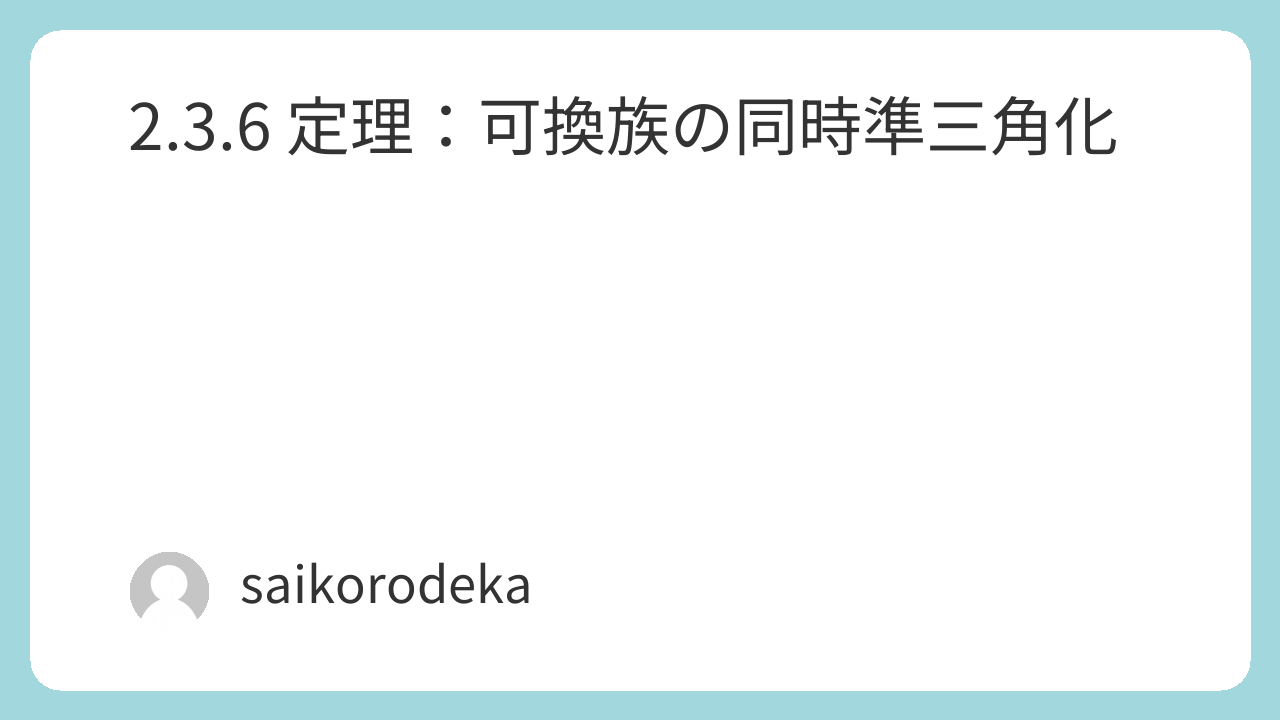
コメント