定理 2.1.9:共役と類似
\( A \in M_n \) が正則行列(可逆行列)であるとします。このとき、次の条件は同値です:
- \( A^{-1} \) が \( A^* \) に類似である。
- ある正則行列 \( B \in M_n \) が存在して、\( A = B^{-1}B^* \) が成り立つ。
証明
まず、ある正則行列 \( B \in M_n \) が存在して \( A = B^{-1}B^* \) が成り立つと仮定します。 このとき、
A^{-1} = (B^*)^{-1} B と書けます。また、類似変換を考えると次のようになります:
B^* A^{-1} (B^*)^{-1} = B B^{-1} = (B^{-1} B^*)^* = A^* よって、\( A^{-1} \) は \( A^* \) に類似であることがわかります。類似変換の行列は \( B^* \) です。
逆に、\( A^{-1} \) が \( A^* \) に類似であると仮定します。すなわち、ある正則行列 \( S \in M_n \) が存在して、
S A^{-1} S^{-1} = A^* が成り立つとします。ここで、\( \theta \in \mathbb{R} \) に対して次のように定義します:
S_\theta = e^{i\theta} S すると、次が成り立ちます:
S_\theta = A^* S_\theta A, \quad S_\theta^* = A^* S_\theta^* A
この2つを加えると、
H_\theta = A^* H_\theta A
ここで \( H_\theta = S_\theta + S_\theta^* \) はエルミート行列です。 もし \( H_\theta \) が特異(非正則)なら、あるゼロでない \( x \in \mathbb{C}^n \) に対して次が成り立ちます:
0 = H_\theta x = S_\theta x + S_\theta^* x
したがって、
-x = S_\theta^{-1} S_\theta^* x = e^{-2i\theta} S^{-1} S^* x つまり、
S^{-1} S^* x = -e^{2i\theta} x となります。ここで \( \theta = \theta_0 \in [0, 2\pi) \) を選び、\( -e^{2i\theta_0} \) が \( S^{-1}S^* \) の固有値でないようにすれば、得られるエルミート行列 \( H = H_{\theta_0} \) は正則となり、かつ
H = A^* H A
を満たします。
行列 B の構成
複素数 \( \alpha \) を \( |\alpha| = 1 \) かつ \( \alpha \) が \( A^* \) の固有値でないように選びます。
次に複素定数 \( \beta \neq 0 \) を使って次のように定義します:
B = \beta(\alpha I - A^*) H
このとき \( B \) は正則であり、私たちは次の恒等式を得たいとします:
A = B^{-1} B^*, \quad \text{すなわち} \quad BA = B^* まず、共役転置を計算します:
B^* = H(\bar{\beta} \bar{\alpha} I - \bar{\beta} A) 一方、
BA = \beta(\alpha I - A^*) H A = \beta(\alpha H A - H)
ここで \( H = A^* H A \) を使うと、
BA = H(\alpha\beta A - \beta I)
したがって、次の条件を満たす \( \beta \) を選べばよいことになります:
\beta = -\bar{\beta} \bar{\alpha} ここで \( \alpha = e^{i\psi} \) とすれば、次の選択が可能です:
\beta = e^{i(\pi - \psi)/2} 以上により、\( A = B^{-1} B^* \) を満たす正則行列 \( B \) の構成が完了します。
補足:ユニタリ行列のブロック構造
ユニタリ行列を 2×2 のブロック行列として表した場合、対角成分以外(オフダイアゴナル)のブロックの階数は等しくなります。また、対角ブロックの階数は単純な関係式により結ばれています。

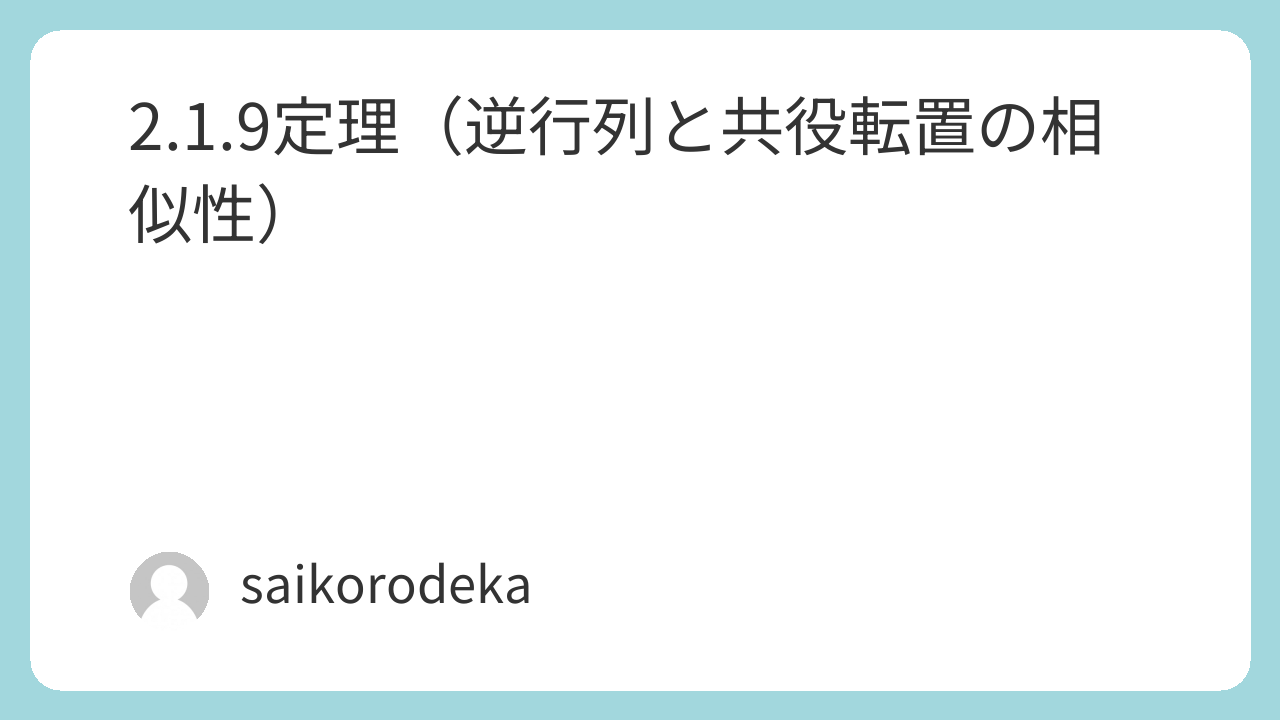
コメント