定理 2.6.4.
2.6.4
無限列 \( A_1, A_2, \ldots \in M_{n,m} \) が与えられ、成分ごとの収束により \(\lim_{k \to \infty} A_k = A\) であるとする。
また \( q = \min\{m, n\} \) とする。
ここで \( \sigma_1(A) \geq \cdots \geq \sigma_q(A) \)、および \( \sigma_1(A_k) \geq \cdots \geq \sigma_q(A_k) \) を、それぞれ \(A\) および \(A_k\) の非増加順に並べた特異値とする。
このとき、各 \( i = 1, \ldots, q \) に対して次が成り立つ:
\lim_{k \to \infty} \sigma_i(A_k) = \sigma_i(A)
証明.
定理の主張が偽であると仮定する。このとき、ある \(\varepsilon_0 \gt 0\) および無限の増加列 \( k_1 \lt k_2 \lt \cdots \) が存在し、任意の \( j = 1,2,\ldots \) に対して
\max_{i=1,\ldots,q} \left| \sigma_i(A_{k_j}) - \sigma_i(A) \right| \gt \varepsilon_0
\tag{2.6.4.1}
となる。各 \( j \) に対して、特異値分解
A_{k_j} = V_{k_j} \Sigma_{k_j} W_{k_j}^*
をとる。ただし \( V_{k_j} \in M_n \)、\( W_{k_j} \in M_m \) はユニタリ行列、\(\Sigma_{k_j} \in M_{n,m}\) は非負の対角成分をもつ行列で、
\mathrm{diag}(\Sigma_{k_j}) =
[\sigma_1(A_{k_j}), \ldots, \sigma_q(A_{k_j})]^T
である。補題 2.1.8 により、さらに部分列 \( k_{j_1} \lt k_{j_2} \lt \cdots \) とユニタリ行列 \( V, W \) が存在して、
\lim_{\ell \to \infty} V_{k_{j_\ell}} = V,
\qquad
\lim_{\ell \to \infty} W_{k_{j_\ell}} = W
が成り立つ。したがって
\lim_{\ell \to \infty} \Sigma_{k_{j_\ell}}
= \lim_{\ell \to \infty} V_{k_{j_\ell}}^* A_{k_{j_\ell}} W_{k_{j_\ell}}
= V^* A W
が存在し、これは非増加順に並んだ対角成分を持つ非負の対角行列となる。これを \(\Sigma\) と書くと、\( A = V \Sigma W^* \) が得られる。特異値の一意性より、
\mathrm{diag}(\Sigma) = [\sigma_1(A), \ldots, \sigma_q(A)]^T
となり、これは (2.6.4.1) と矛盾する。よって定理が証明された。 □
特異値分解におけるユニタリ因子は決して一意ではない。例えば、もし \( A = V \Sigma W^* \) であれば、\( V \) を \(-V\) に、\( W \) を \(-W\) に置き換えることもできる。
次の定理は、特異値分解において一組のユニタリ因子が与えられたときに、他のすべての可能なユニタリ因子の組をどのように構成できるかを明示的かつ有用な形で記述する。
行列解析の総本山
総本山の目次📚
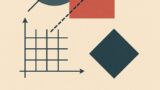
記号の意味🔎


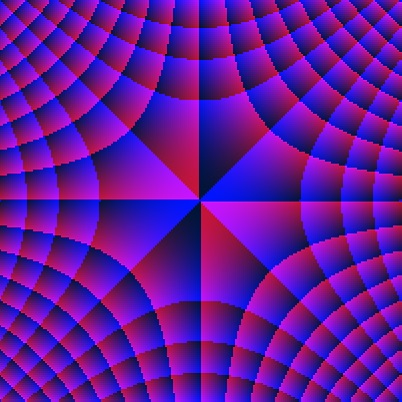

コメント