定義 1.1.4.
\( A \in M_n \) の スペクトルとは、\( A \) の固有値となるすべての \(\lambda \in \mathbb{C}\) の集合であり、この集合を \(\sigma(A)\) で表す。
与えられた \( A \in M_n \) に対して、この時点では \(\sigma(A)\) が空かどうか、また空でない場合には有限個の複素数を含むのか無限個含むのかはまだわからない。
練習問題
もし \( x \) が \( A \) の固有値 \(\lambda\) に対応する固有ベクトルであるならば、\( x \) の任意のゼロでないスカラー倍も \(\lambda\) に対応する \( A \) の固有ベクトルであることを示せ。
もし \( x \) が \( A \in M_n \) の固有値 \(\lambda\) に対応する固有ベクトルならば、それを正規化して単位ベクトル
\xi = \frac{x}{\|x\|_2} を作ることは便利である。この \(\xi\) も依然として \(\lambda\) に対応する \( A \) の固有ベクトルである。ただし、正規化によって \(\lambda\) に対応する固有ベクトルが一意に定まるわけではない。実際、任意の \(\theta \in \mathbb{R}\) に対して、\((\lambda, e^{i\theta} \xi)\) は \( A \) の固有値–固有ベクトルの組となる。
練習問題
もし \( A x = \lambda x \) ならば、\(\overline{A} \, \overline{x} = \overline{\lambda} \, \overline{x}\) が成り立つことを確認せよ。
そして \(\sigma(\overline{A}) = \sigma(A)\) である理由を説明せよ。さらに、\( A \in M_n(\mathbb{R}) \) かつ \(\lambda \in \sigma(A)\) ならば、\(\overline{\lambda} \in \sigma(A)\) である理由を説明せよ。
たとえ他に重要な性質がなくても、固有値と固有ベクトルは代数的に興味深い。式 (1.1.3) によれば、固有ベクトルとは「行列 \( A \) による乗算がスカラー \(\lambda\) による乗算と同じになる」ようなゼロでないベクトルである。
練習問題
次の行列を考える:
A = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \in M_2 このとき、\( 3 \in \sigma(A) \) であり、
\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} は対応する固有ベクトルである。実際、
A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} が成り立つ。また、\( 5 \in \sigma(A) \) である。固有値 \( 5 \) に対応する固有ベクトルを求めよ。
練習問題
行列 \( J_n \) を、すべての成分が 1 の \( n \times n \) 行列とする。
また、すべての成分が 1 の \( n \)-ベクトル \( e \) を考える。
さらに、\(\{ e_1, \dots, e_n \}\) を \(\mathbb{C}^n\) の標準基底として、\( x_k = e - n e_k \) とおく。
\( n = 2 \) の場合、\( e \) と \( x_1 \) が \( J_2 \) の一次独立な固有ベクトルであり、それぞれの固有値が \( 2 \) と \( 0 \) であることを示せ。
\( n = 3 \) の場合、\( e, x_1, x_2 \) が \( J_3 \) の一次独立な固有ベクトルであり、それぞれの固有値が \( 3, 0, 0 \) であることを示せ。
一般に、\( e, x_1, \dots, x_{n-1} \) が \( J_n \) の一次独立な固有ベクトルであり、それぞれの固有値が \( n, 0, \dots, 0 \) であることを示せ。
練習問題
次の行列の固有値が \( 1 \) と \( 4 \) であることを示せ。
A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} ヒント:固有ベクトルを用いよ。\( A = 4I - J_3 \) と書き、前の練習問題を利用する。
多項式の行列への適用
次数 \( k \) の多項式
p(t) = a_k t^k + a_{k-1} t^{k-1} + \cdots + a_1 t + a_0, \quad a_k \neq 0 (係数は実数または複素数)に対し、\( A \in M_n \) を代入することはよく定義されている。
なぜなら、正方行列のべき乗の線形結合を作ることができるからである。
定義により、
p(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I とし、慣習として \( A^0 = I \) とする。
次数 \( k \) の多項式 (1.1.5a) が モニックであるとは、\( a_k = 1 \) の場合をいう。もちろん、ゼロ多項式はモニックではない。
なお、\( a_k \neq 0 \) ならば、\( a_k^{-1} p(t) \) は常にモニックになる。
代数学の基本定理により、次数 \( k \geq 1 \) のモニック多項式 (1.1.5a) は、必ず \( k \) 個の複素数(または実数)の一次因子の積に分解できる:
p(t) = (t - \alpha_1) \cdots (t - \alpha_k)
この因数分解は、因子の順序を除いて一意である。この表示から、\( p(\alpha_j) = 0 \) が \( j = 1, \dots, k \) について成り立つので、各 \(\alpha_j\) は \( p(t) = 0 \) の根であることがわかる。逆に、もし \( p(\beta) = 0 \) ならば、\(\beta \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}\) である。したがって、次数 \( k \geq 1 \) の多項式は高々 \( k \) 個の異なる根しか持たない。
積の中には重複因子が含まれる場合がある。例えば:
p(t) = t^2 + 2t + 1 = (t + 1)(t + 1)
この場合、因子 \((t - \alpha_j)\) の繰り返し回数を \(\alpha_j\) の 重複度という。
この因数分解 (1.1.5c) により、行列に対しても次のような因数分解が得られる:
p(A) = (A - \alpha_1 I) \cdots (A - \alpha_k I)
そして、\( p(A) \) の固有値は、\( A \) の固有値と簡単な関係で結びついている。
行列解析の総本山
総本山の目次📚

記号の意味🔎


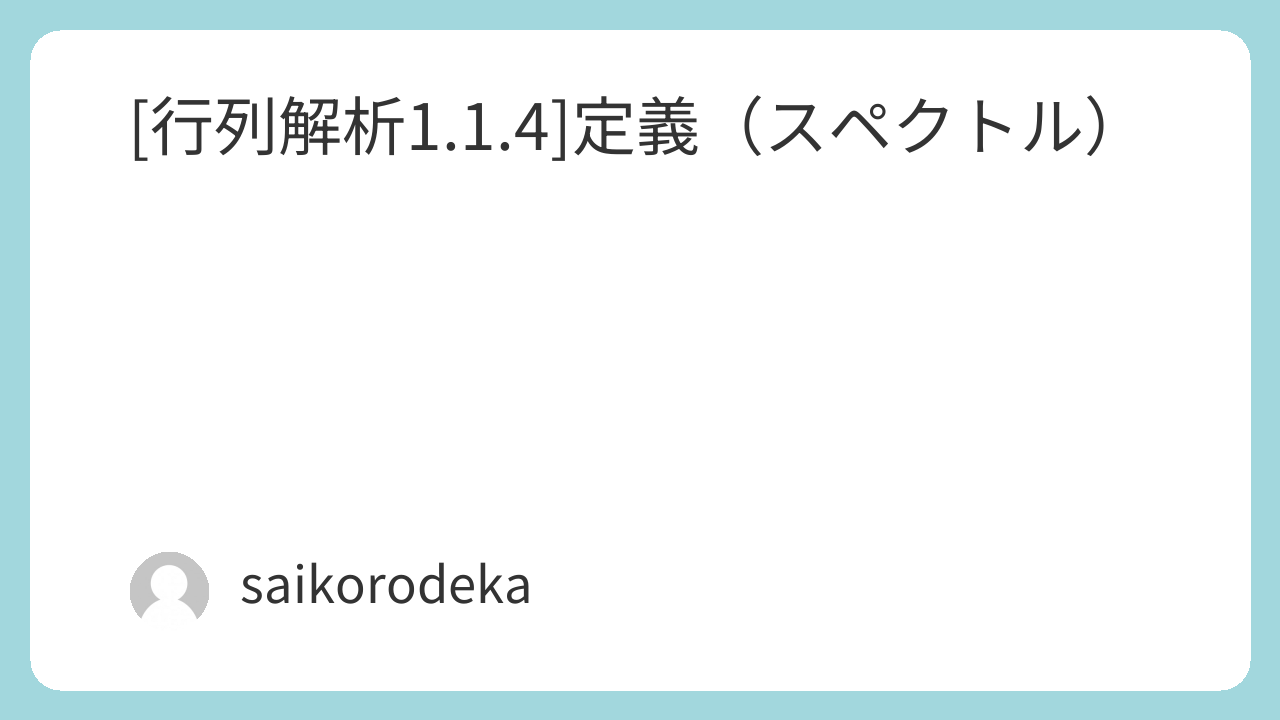

コメント